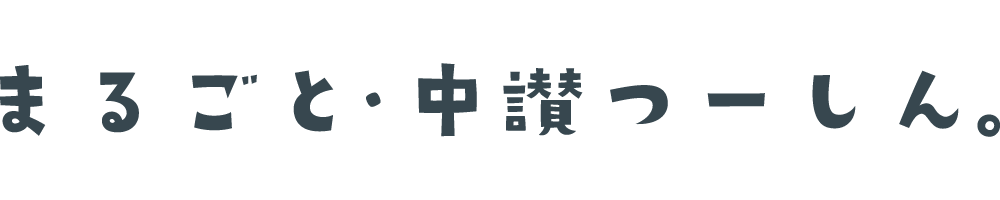今回は宇多津町西町東周辺のおすすめスポットということで、うたづの厄除け大師こと郷照寺をご紹介します!
宇多津町西町東の郷照寺
郷照寺
宇多津町の南、青ノ山のふもとの高台に建ち、境内からは臨海の宇多津の町と瀬戸大橋を望む。
奈良時代(8世紀初め・神亀2年(725))、行基菩薩が開創し仏光山・道場寺と称していた。本尊の阿弥陀如来は行基の作といわれる。
後に、弘仁6年(815)弘法大使42歳のころ、この地を訪れ、自作のご尊像を刻み厄除のご誓願をなされたことから「厄除うたづ大師」として信仰を集めている。その後、正応元年(1288)時宗の開祖・一遍上人によって浄土易行の法門の伝統が加わり、真言・念仏の2教の法門が伝わった。元亀、天正の兵火で伽藍を焼失した。
江戸時代に入り、高松藩主・松平頼重により再興された。その際、宗旨を真言宗とともに一遍上人を偲んで時宗も奉持することにし、寺名も78番「郷照寺」と改めた。真言宗と時宗の両宗にわたる寺としては四国札所唯一の寺である。引用元:郷照寺公式サイトより
確かに、地元の人には昔から厄除けと言えば!という感じで知られていますよね。筆者も厄年には「今年は郷照寺行っときなよ」と言われ、なんか病院みたいだなと思ったのを覚えています。
山門をくぐり、石段をのぼるとまず大きな鐘楼が目に入ります。さらに境内に足を進めると、あ!やっぱりありますね、厄年の早見表。次は何年後かな・・・とチェックしつつ、奥へ。本堂に祀られている阿弥陀如来像は鎌倉時代末期のものだそうで、県指定の有形文化財にもなっているそうです。
さて、厄除けに来たのなら大師堂に行くのを忘れてはいけません。本堂の左にある階段をのぼると厄除け大師のお堂が見えてきます。余談ですが大師堂の手前、香炉の屋根のあたりからお堂にかけての天井には、とりどりに色付けされた花々がまるで花紋の刺繍のように並んでいてとっても綺麗なんですよ。初詣等で混んでない時期ならぜひ立ち止まって眺めてみてください。・・・あ、ねりきりにも似てるなぁ。
こちらは淡島大明神です。女性の神様というと弁天様を思い浮かべますが、江戸時代に流行病からお産の後に体調を崩す女性のためにと祀られた神様だそうなので、妊婦さんには特に御利益がありそうですね。
「KBN×まるごと中讃つーしん」コラボ動画
情報を網羅する人気サイト「まるごと・中讃つーしん (まるちゅー:旧 丸亀つーしん)」 と、坂出・宇多津のケーブルテレビ局「KBN」、そして坂出・宇多津のコミュニティFM局の「エフエム・サン」がコラボをして動画内でさらに詳しくご紹介しています!!
「KBN × まるごと中讃つーしん」コラボ動画↓↓↓
ちなみにちなみに!この郷照寺の山門を下ったすぐ下にある地蔵堂の向かいにある、高橋地蔵餅本舗っていうお店のお餅がめっちゃ美味しいんですよ!季節にもよりますが、筆者は草餅がイチオシです。郷照寺にお参りに詣でたら、そちらにもぜひ足をはこんでみてくださいね。
住所:〒769-0296 香川県綾歌郡宇多津町1435番地
電話番号:0877-49-0710 ※受付時間9:00~16:00
関連リンク:郷照寺公式サイト
※掲載情報は記事作成当時のものです。